こんにちは、モモです!
最近、話題になっている「GLM‑4.5」と「GLM‑4.5 Air」って知っていますか?どちらもオープンソースAIとして登場した注目のモデルで、DeepSeekとの違いや使いやすさが気になるところです。
特に、軽くて使いやすいGLM‑4.5 Airは、個人や小さなチームでも扱いやすそうですよね。今回は、この2つのAIが何を目指していて、どんな特徴があるのかを、わかりやすくご紹介します!これからAIをもっと身近に使っていきたい方にぴったりの内容なので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね♪
 モモちゃん
モモちゃん-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
GLM‑4.5とはどんなオープンソースAI?
-700-x-366-px-5.gif)
-700-x-366-px-5.gif)



-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)



GLM‑4.5は、中国のTHUDM(清華大学)が開発したオープンソースAIで、複数の言語に対応できる多目的モデルです。3550億のパラメータを持ちながら、実際に使うのは320億と効率的なのがポイントです。
ハイブリッドな推論モードを備えており、状況に応じて反応の仕方を変えることができます。この構造により、軽快な動作としっかりとした応答を両立させています。オープンソースなので、個人や企業でも自由に使えるのも大きな特徴です。
GLM‑4.5の基本的な特徴
GLM‑4.5は、非常に大きなパラメータを持つAIですが、実際に動かす際は一部の部分だけを使うしくみになっています。これは「MoE(Mixture of Experts)」という仕組みで、全部を動かすよりも軽く、でもしっかり考えた答えを出すように工夫されています。
さらに、日本語を含む多言語に対応しているので、英語だけでなく日本語のやりとりにも使えます。個人でも試しやすく、設定もシンプルなのが嬉しいポイントですね。
GLM‑4.5の推論モードとは?
GLM‑4.5には「思考モード」と「非思考モード」という2つの動き方があります。思考モードでは、質問にしっかり考えてから答えを出します。一方、非思考モードでは、すぐに反応することを優先します。
使う場面に合わせて切り替えられるので、スピードを重視する時と、内容を重視する時とで調整できるのがポイントです。このしくみがあることで、柔軟に使えるAIとして評価されているんです。
GLM‑4.5が公開された意味
GLM‑4.5はMITライセンスで公開されているので、商用でも個人でも自由に使えるようになっています。こうしたAIは一般的に制限があることが多いのですが、GLM‑4.5は制限がゆるく、いろいろなプロジェクトに活用できます。
そのため、企業での導入にも向いていますし、個人の開発にも適しています。オープンソースだからこそ、多くの人が試せるというのが大きなポイントですね。
GLM‑4.5 Airの特徴と使いやすさ
-700-x-366-px-8.gif)
-700-x-366-px-8.gif)



-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)



GLM‑4.5 Airは、GLM‑4.5の派生モデルとして設計されていて、より軽くて使いやすいのが特徴です。パラメータ数を減らして動作を軽くしながらも、必要な機能をしっかり備えています。これは主にチャットボットやエージェント向けに作られており、日常的な対話やサポート業務などに適しています。
オープンソースとして公開されているので、誰でも自由に利用できるのが嬉しいポイント。パソコンのスペックに余裕がない場合でも試しやすく、個人や中小企業でも使いやすいモデルになっています。
GLM‑4.5 Airの軽量化ポイント
GLM‑4.5 Airは、パラメータ数がGLM‑4.5より少なく、全体の動作が軽くなっています。これによって、処理速度が速くなり、より手軽に使うことが可能です。
動作環境の負担が少ないため、普通のパソコンや小さなサーバーでも扱いやすく、導入のハードルが下がります。とはいえ、必要な応答の正確さは保たれているので、日常的なチャットや質問応答には十分な性能を持っています。
実際の利用シーンとメリット
GLM‑4.5 Airは、特にチャットボットやエージェント型AIとしての利用が想定されています。例えば、カスタマーサポートや情報案内、簡単な相談対応などで活用されやすいです。
軽さを活かしてレスポンスが速く、ユーザーのストレスを減らせるのがメリット。また、オープンソースなので、開発者が自由にカスタマイズや改良ができる点も大きな魅力となっています。
GLM‑4.5 Airの今後の展望
今後はGLM‑4.5 Airの軽量さを活かして、さらに多様な環境での利用が期待されています。特に、クラウドだけでなくローカル環境でも手軽に使えることで、より広いユーザー層に届くでしょう。
オープンソースのため、多くのコミュニティが改良や拡張に関わることが可能で、使い方や対応言語の幅も徐々に広がっていくと考えられています。こうした動きは、AIを身近にする一歩になりそうです。
GLM‑4.5とGLM‑4.5 Airのメリットと課題
-700-x-366-px-2-2.gif)
-700-x-366-px-2-2.gif)



-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)



GLM‑4.5とGLM‑4.5 Airはそれぞれ特徴が異なり、使い分けることでさまざまな場面に対応できます。GLM‑4.5は大規模で高精度な応答が得られやすい一方、動作が重いため高性能な機器が必要です。
逆にGLM‑4.5 Airは軽量化されていて動作が速く、手軽に利用できますが、大きなモデルに比べると処理できる情報量が少なくなります。
どちらもオープンソースなので、カスタマイズや改良が自由にできますが、導入や運用には専門知識が多少求められます。これらの特徴を理解して、自分の目的に合ったモデルを選ぶことが大切です。
GLM‑4.5のメリットとデメリット
GLM‑4.5は大きなモデルなので、複雑な質問や多言語対応に優れています。より正確で詳しい回答が期待できるのが強みです。
しかし、その反面、動作には高い計算資源が必要で、導入コストやメンテナンスがかかります。高性能な環境が必要なため、誰でも簡単に扱えるわけではないのが課題です。
GLM‑4.5 Airの良い点と注意点
GLM‑4.5 Airは軽くて速い動作が特徴で、パソコンや小規模なサーバーでも扱いやすいです。日常的なチャットや簡単な質問応答には十分な性能を持っています。
ただし、モデルが小さい分、複雑なタスクや細かいニュアンスの理解には限界があります。利用シーンを選ぶことが重要です。
使い分けのポイントと選び方
GLM‑4.5は情報量が多く、重い処理を求める時に適しています。一方、GLM‑4.5 Airは軽くて速さを求める時に向いています。予算や使いたい用途、環境のスペックに応じて使い分けるのが賢い選び方です。
また、オープンソースならではの自由度を活かし、カスタマイズして自分のニーズに合わせるのもおすすめです。
まとめ:GLM‑4.5とGLM‑4.5 Airの特徴と選び方
-700-x-366-px-3.gif)
-700-x-366-px-3.gif)



-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
GLM‑4.5とGLM‑4.5 Airについてご紹介しましたが、どちらにも良いところがありますね。GLM‑4.5はしっかりした性能があるので、重たい処理や専門的な作業に向いています。
一方で、GLM‑4.5 Airは軽くて動きやすいので、ふだんのちょっとした作業や手軽に試したいときにぴったりです。どちらを選ぶかは、自分が何をしたいかで変わってきます。使う目的や環境に合わせて、うまく選んで活用してみてくださいね。




従来の記事作成と異なり、AIを使うことで大量のデータから
最適な情報を選び出し、コスパ良く記事を生み出すことが可能です。
時間の節約、コスト削減、品質の維持。
AI記事作成代行サービスは、効率よく質の高い記事を作成いたします。

-700-x-366-px-1-2.gif)

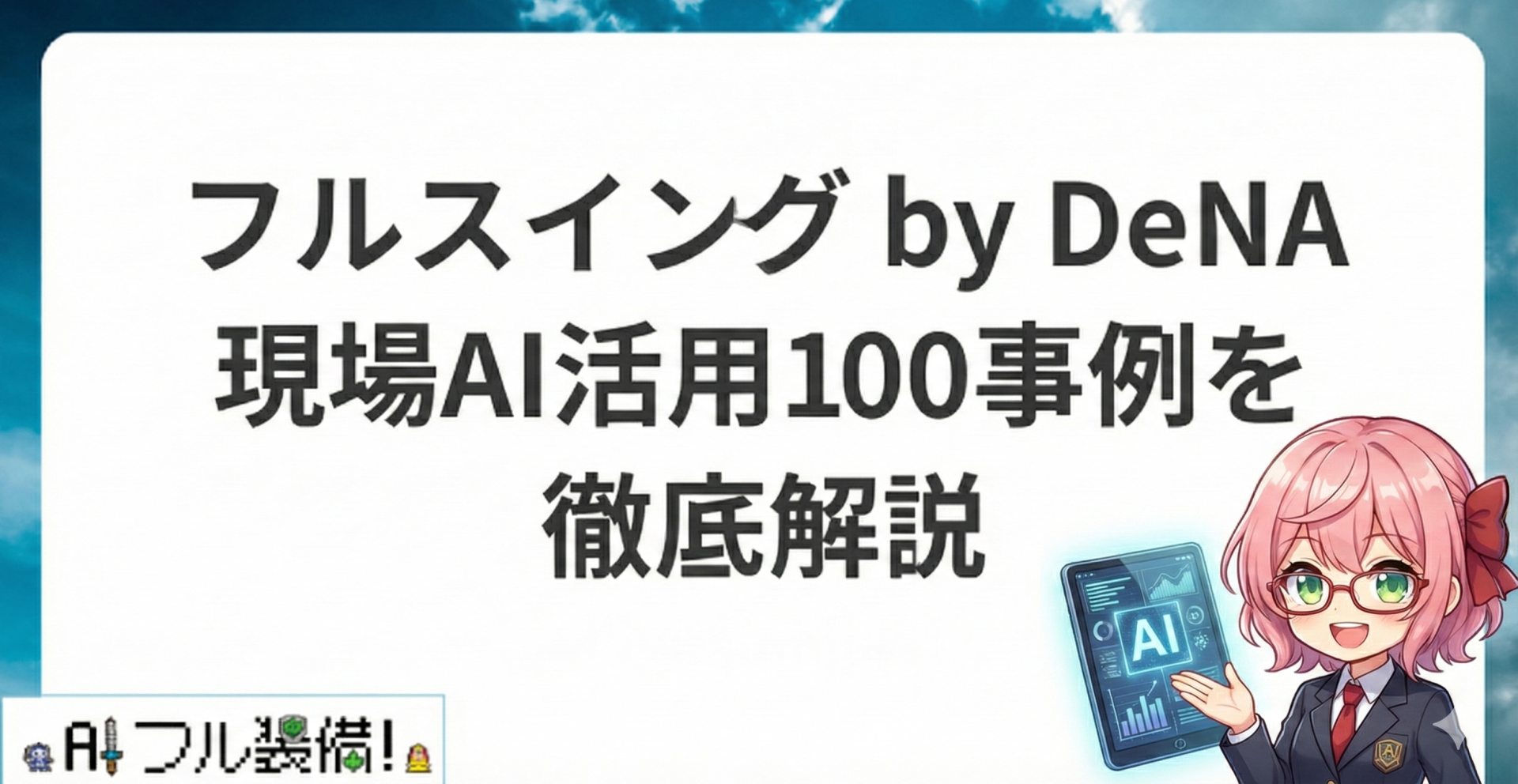
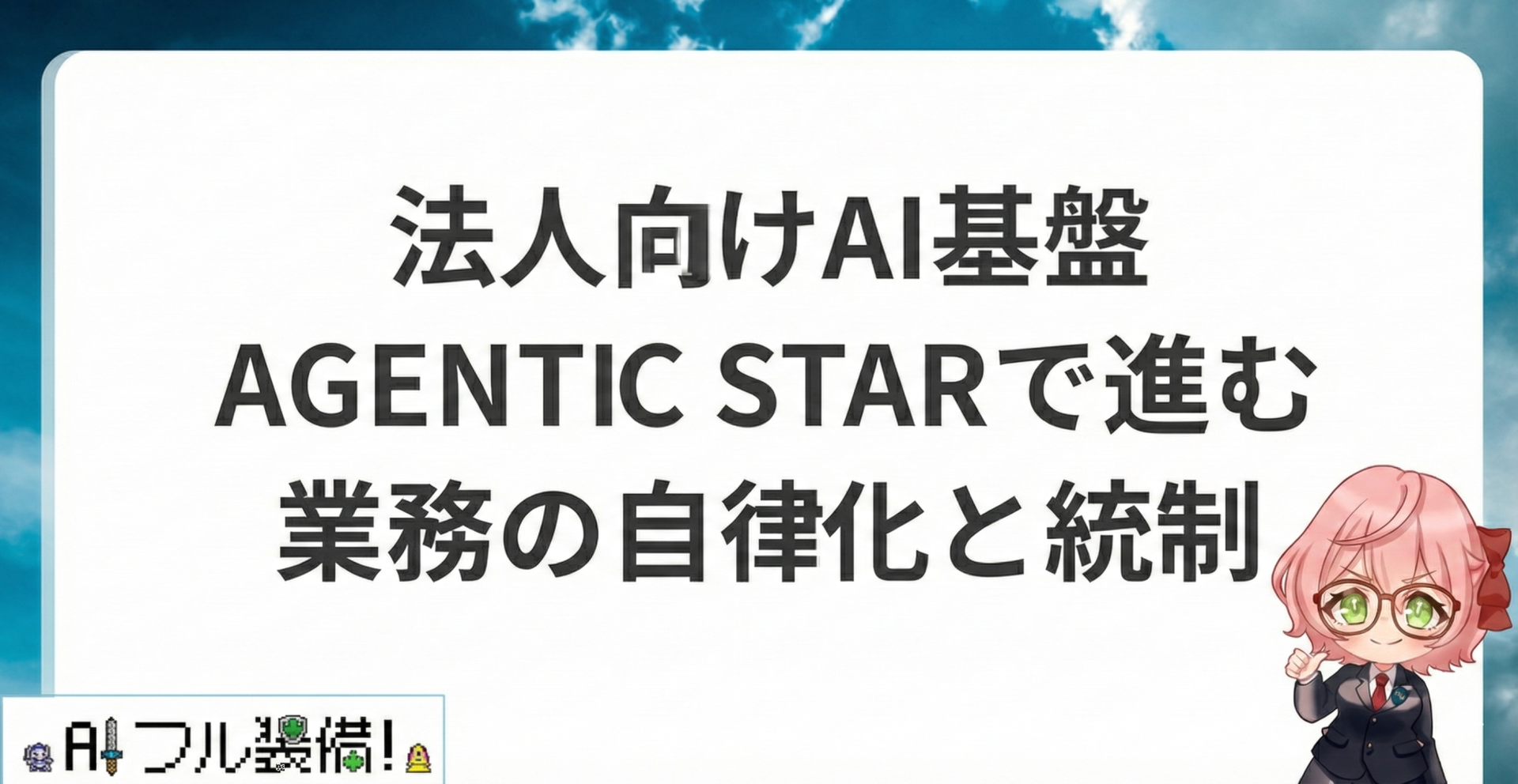
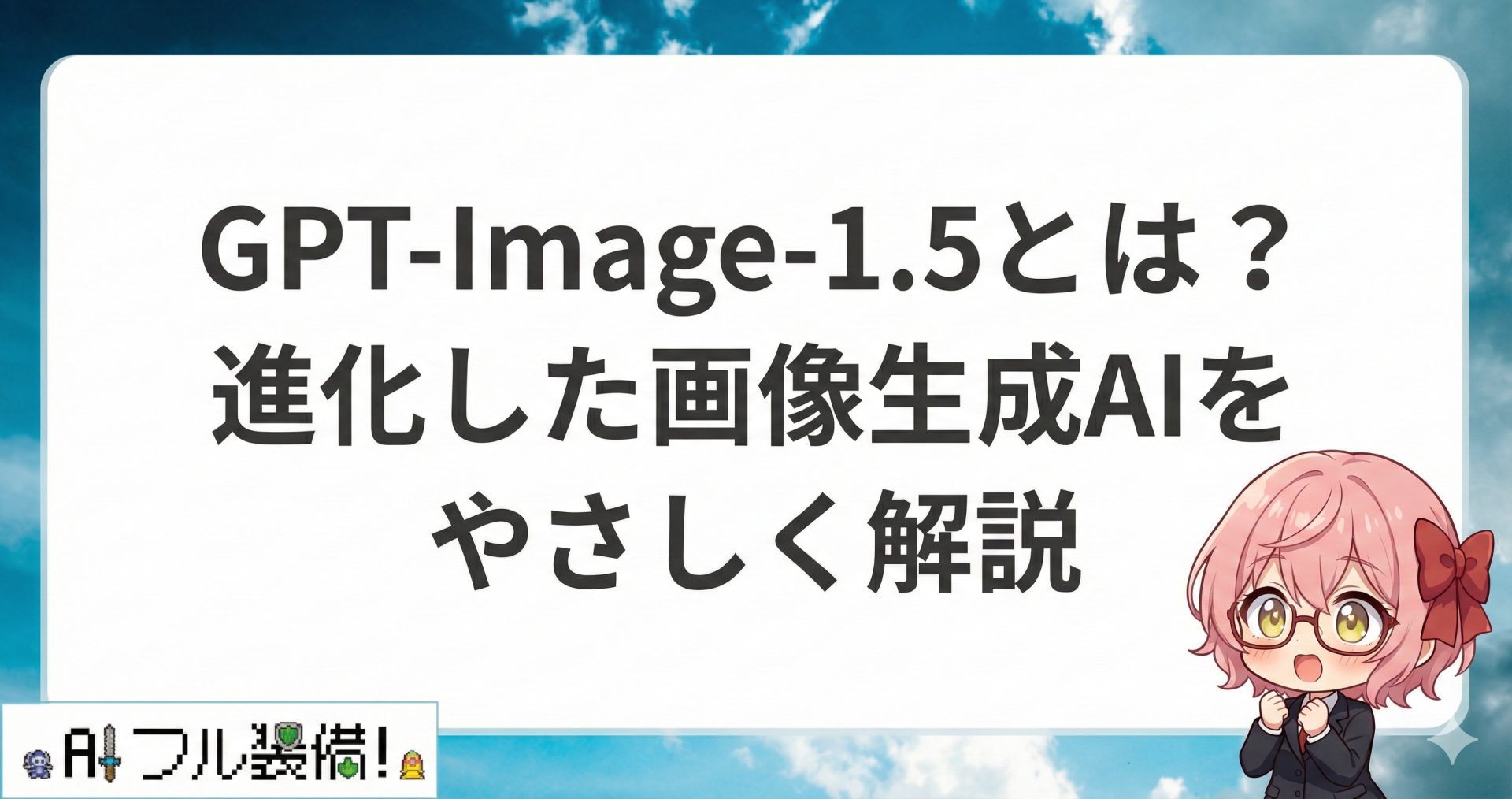
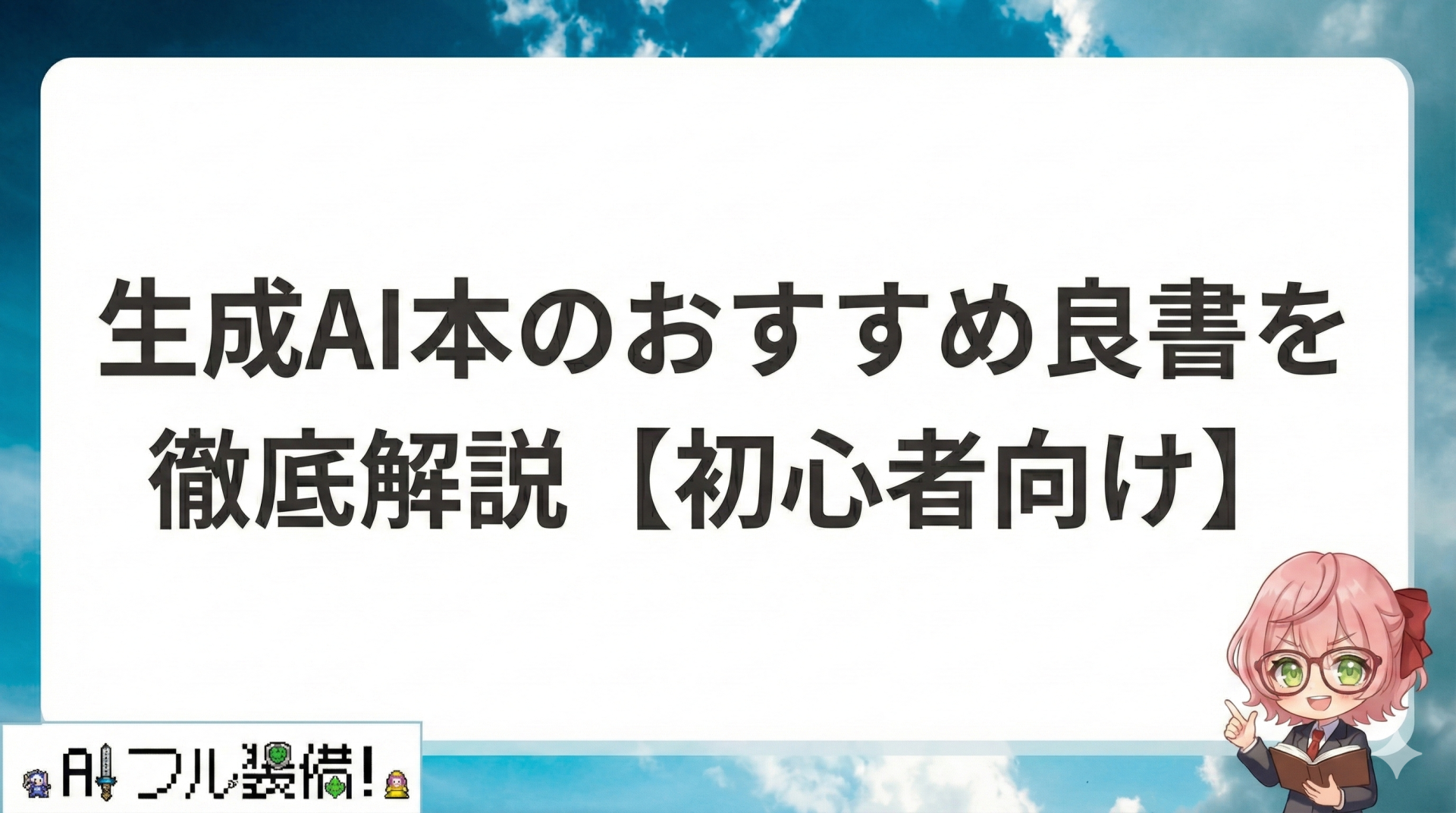
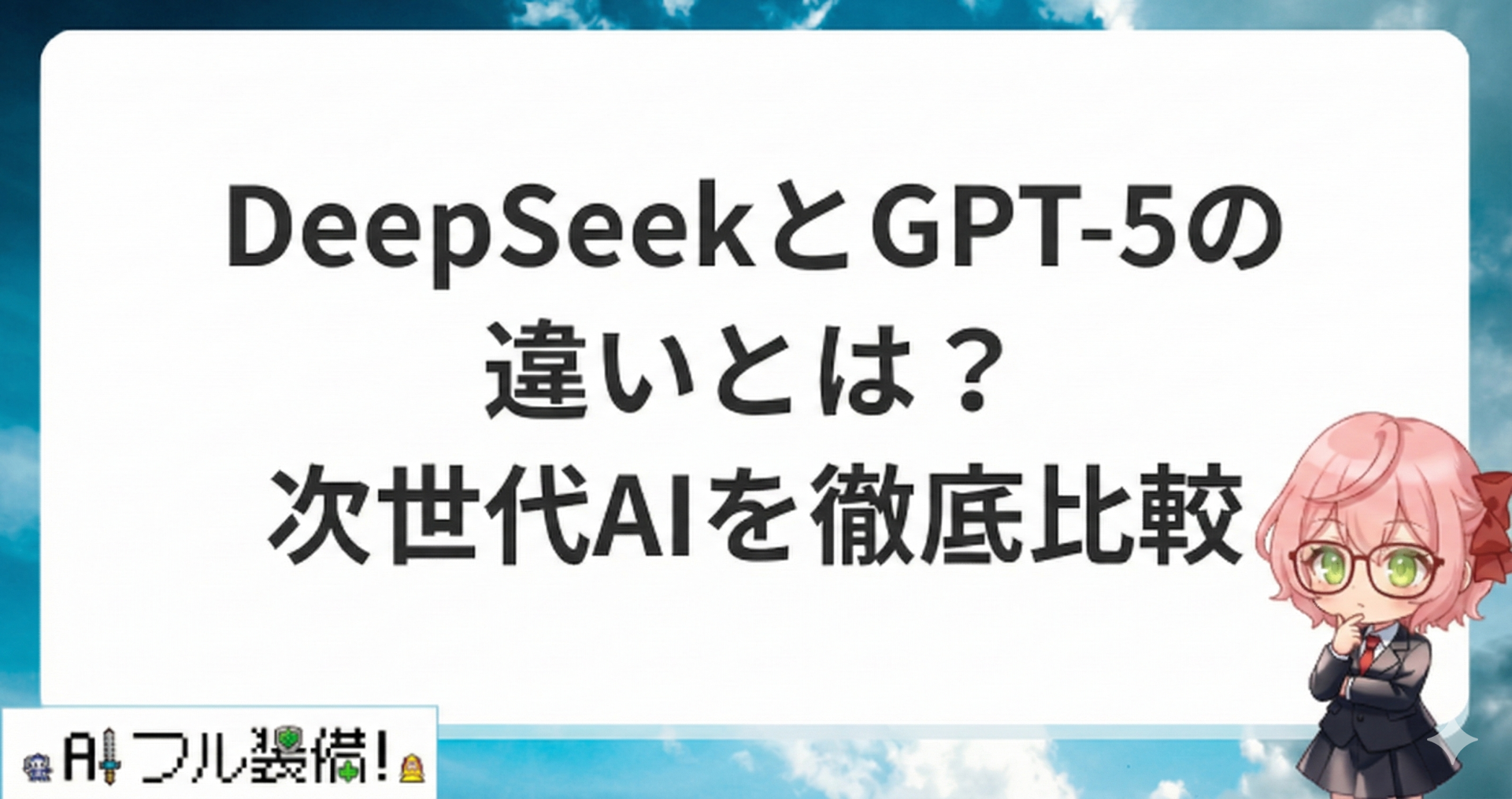
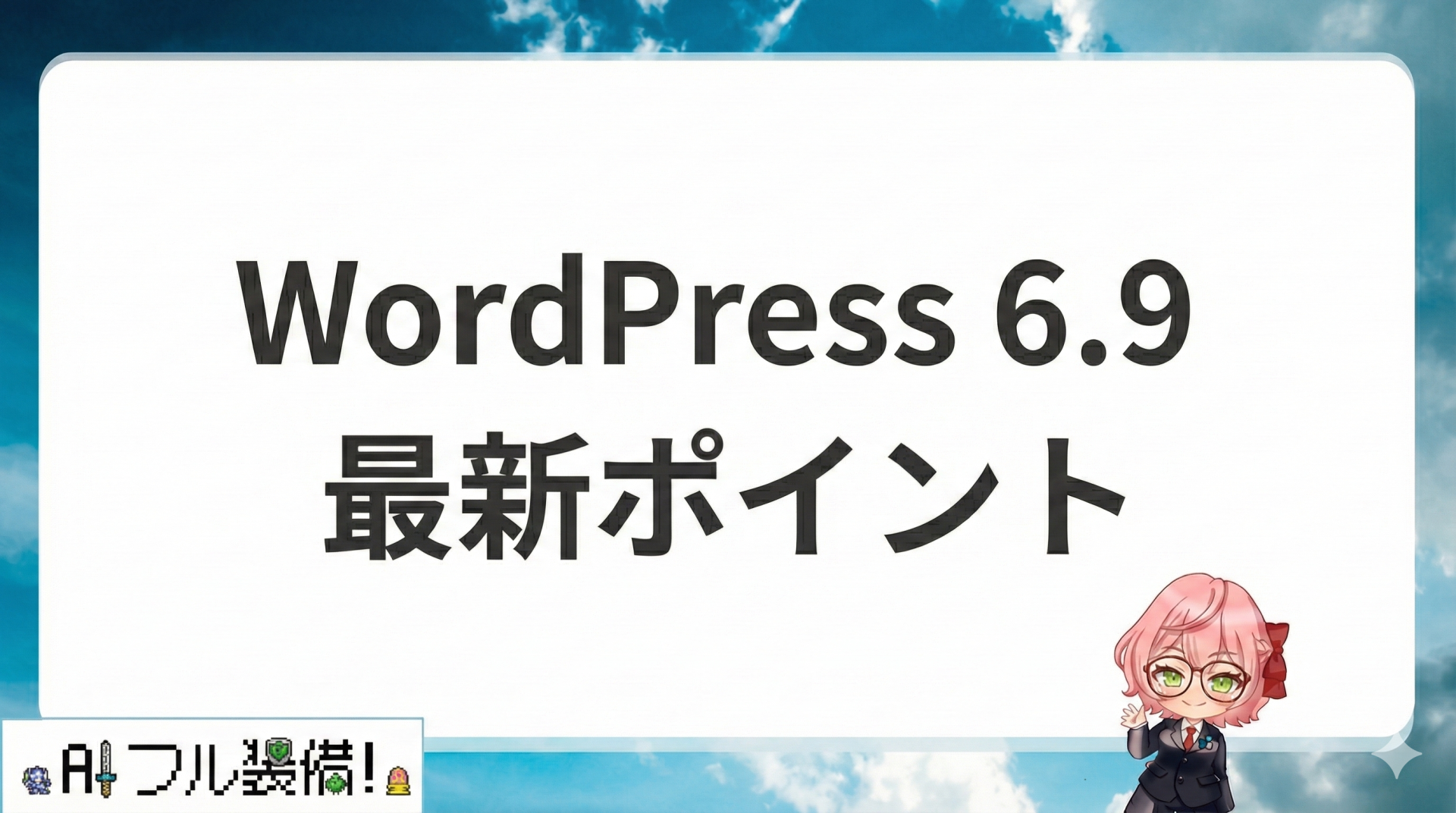


コメント